Blog
2025.05.26
鉄鋼と共にトランプ関税のターゲットとなったアルミニウム。飲料の缶や容器、電子機器、自動車や飛行機、建物のサッシなど用途は多岐にわたります。日本国内では4万5千人を擁する2.2兆円の産業。原料は100%輸入に依存していますが、途上国の需要拡大による将来的な原料確保の危機や、リサイクル材の開発でも注目が集まっています。
今日は、アルミニウム板材の国内最大級の製造拠点である株式会社UACJ名古屋製造所を訪問し、業界が抱える課題と対策について意見交換をしました。1937年に開催された名古屋汎太平洋平和博覧会の跡地に、現在の製造所の前身となる軽合金の製造所が建設されたのは1941年。当時は零戦の工場が周辺に点在していました。今も東京ドーム10個分の広大な土地にアルミニウムの圧延・押出加工、研究開発センターが集約されています。

アルミニウム板は鉄鋼と同様に圧延の技術で作られます。400〜600℃の棒状のアルミの塊が圧延されて、毎分2000m(時速120km!)の速さでコイルに巻き取られていく様子は圧巻です。一方でアルミは鉄と異なり金型を使って押出プレスで製造されるものもあります。親指くらいの大きさの自動車部品に0.1ミリの微小な穴が24個並んだ製品を拝見しましたが、精緻さにビックリしました。加工もさることながら、製造の上流工程で質の高い合金を作れるかどうかが製品の質を決めるとのこと。
1.合金開発
第二次大戦前に戦闘機への需要から、ドイツの超超ジュラルミンを模して航空機用合金の開発が進みました。零戦の主翼桁材に使用することで一機あたり30kg軽量化したそうです。近年では自衛隊のP1哨戒機など国内の防衛装備や、新幹線の構体にも多様な合金が使われています。日本から国際登録した合金は14種類にも及ぶとのこと。
2.缶材料
日本では年間210億缶もの需要がある飲料用のアルミニウム缶。日本で初めてオールアルミ缶が登場した1971年から改良が重ねられてきましたが、缶胴と缶蓋では材質や製法が若干異なります。使用済みアルミ缶の回収率が97%を超える一方で、再び飲料缶に使われるのは73%程度。使用済み缶の海外流出防止と、缶蓋材のリサイクル拡大が課題です。
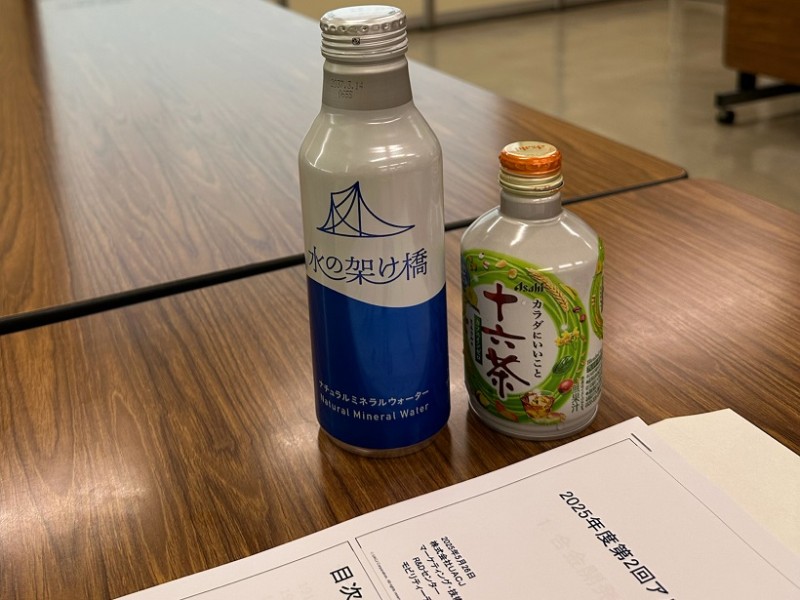
3.エアコン用アルミニウム塗装フィン
私も初めて知ったのですが、エアコンの中には薄いアルミ板が並び、熱交換器の役割を果たしています。フィンに特殊な塗装を施すことで、結露水が滴り落ちることがないよう工夫されています。廃エアコンからフィン材を回収してリサイクルする取組も進んでいます。
4.自動車材・自動車部品
車体軽量化による燃費向上を背景に、車体にもアルミニウム合金版が使われ始めています。現状では自動車1台あたりアルミ使用料は170kg程度ですが、2050年頃には288kgまで拡大するとの試算も。アルミの新地金は製造段階でCO2排出量が非常に多いため、CO2原単位が10分の1と低いリサイクルアルミを活用した材料開発が進んでいます。廃車から集めたスクラップの回収・再利用も始まっており、選別を行う方法や不純物の除去などが課題です。
自動車部品としてアルミの利用が拡大しているのは、電気自動車の電池筐体や、フロントバンパーなど。特にフロントバンパーは何度も強度試験を重ね、乗員だけでなく歩行者も守る開発がなされています。
5.縦型高速双ロール鋳造実験機
活用範囲の広いアルミニウムですが、最大の難点は原材料であるボーキサイトから製錬する際に大量の電気を消費しCO2負荷が非常に大きいことです。一方で、アルミをリサイクルすればCO2負荷は30分の1まで軽減できます。アルミスクラップから再生アルミを製造するための実証実験として、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の国家プロジェクトとして導入された実験機を拝見しました。リサイクルの障害となるのは、①元の合金の組成の違い、②スクラップの選別が困難、③スクラップの中の不純物など。ユーザー企業も参画して実用化に向けた開発に取り組み、2030年以降に年間20万トンの量産化、2050年以降に業界全体で1,800万トン規模のCO2削減を目指しています。
巨大な装置の中をアルミが通っていく迫力のある見学でしたが、残念ながら写真撮影は禁止でした。海外への技術流出の恐れは深刻な問題で、日本の産業空洞化を防ぐためにも、特許による保護はもちろん機密保持も重要です。
トランプ大統領がアルミニウムを関税引上げのターゲットにしたという事実は、アルミニウムが国家にとって重要な物資であることの証左でもあります。また、自動車関税の影響が早くも日本国内のアルミ製造に悪影響を及ぼしているという情報もあります。
BtoBの物資の動向は一般消費者には見えにくいため、今回のような製造現場への訪問と業界の方々との直接の意見交換は大変貴重であり、今後の経済安全保障の議論にも活きてくるものと感じました。
